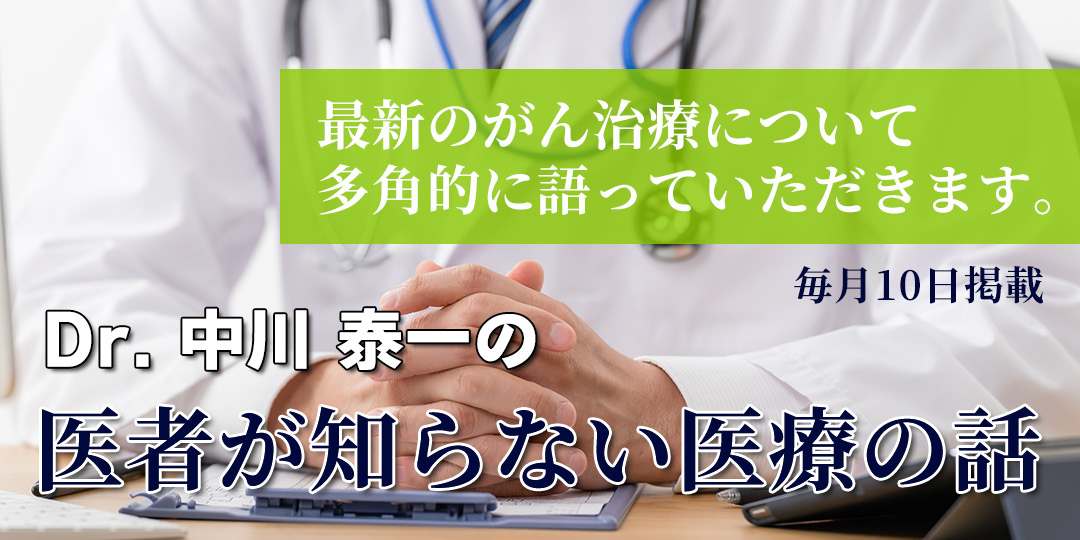前回ではとかく「体内での幹細胞増加」と言うと、単に体内の幹細胞を増やす事と考えがちだが、「増殖」と「動員」がある事。「増殖」とは幹細胞を増やすことであり、「動員」とは幹細胞を増やすのではなく、ある場所に幹細胞を誘導、集中させること。そして、現在のところ「動員」の方が実用化に近いという事で続きを。
7. 非造血組織では「ニッチの再構成」と「腫瘍リスク」の距離がさらに近い
腸、皮膚、肝、筋などの組織常在幹細胞は、自己複製と分化が強く結びついており、“増殖”はそのまま腫瘍化の近傍にある。腸上皮の幹細胞マーカーとしてleucine-rich repeat-containing G-protein coupled receptor 5(LGR5)が同定され、Wntシグナルが幹細胞維持の基盤であることが示されている。
Wnt強度を増強する因子としてR-spondin(RSPO)が知られ、LGR4/5と相互作用してWnt受容体量を調節することでシグナルを増幅する。
一方で、RSPO–LGR5軸はがん文脈とも強く交差し、Wnt増強は“再生”と“腫瘍促進”を同じ方向に押しうる。従って、非造血組織でのin vivo増殖誘導は、(1)局所・短時間・可逆、(2)損傷後の狭い時間窓、(3)腫瘍抑制系(p53経路など)を壊さないという制約の中で設計されるべきだ。
8. “部分的リプログラミング”は増殖と若返りを同時に触るが、最も危険な刃でもある
研究の最前線として、Oct4(POU5F1), Sox2, Klf4, c-Myc のいわゆるYamanaka factorsを短期間・周期的に発現させる partial reprogramming がある。早老モデルで短期周期的OSKM発現が老化指標の改善や寿命延長に関連する報告があり、エピゲノム再編成を介した“若返り”と再生能改善が注目されている。
しかし、in vivoでのリプログラミングは腫瘍化と表裏一体であり、途中停止・不完全な状態が腫瘍形成に結びつくことが示された研究もある。
研究者としての要点は、部分的リプログラミングを「幹細胞を増やす技術」と短絡しないことだ。実態は、(A)クロマチンアクセシビリティの再編、(B)senescence-associated secretory phenotype(SASP)を含む炎症・ストレス応答の再配線、(C)ミトコンドリア代謝やoxidative phosphorylation(OXPHOS)の再構成、(D)ECMプログラムの攪乱、といった多層変化の同時発生である。
したがって、臨床応用を視野に入れるなら、全身OSKMではなく、組織特異的・細胞型特異的・超短期の発現制御、あるいはOSKMに相当する下流ネットワークを“より狭く”触る分子設計が必須になる。
9. 神経—免疫—幹細胞軸:自律神経はニッチの時刻合わせ装置だ
骨髄ではautonomic nervous system(ANS)、特に交感神経がCXCL12発現やニッチ機能に影響し、日内変動やストレス応答と造血動態を結びつける概念が整理されている。
この視点を他組織へ拡張すると、再生医療は「幹細胞+増殖因子」ではなく、神経性調節(血流、代謝、免疫トーン)を含む生体リズム制御として再定義される。たとえば損傷後の局所血流・低酸素・交感神経トーンは、免疫細胞の動員やサイトカイン勾配を変え、結果として幹細胞の休眠解除や分化方向を変える可能性がある。研究設計では、薬剤やバイオマテリアルの効果を評価する際に、ANSや炎症状態のベースラインを揃えないと結果が不安定になる点が実務上の落とし穴だ。
10. バイオマテリアルと局所DDSは「増殖刺激の危険域」を狭めるための必須技術だ
非造血組織でのin vivo増殖誘導を安全域に収める鍵は、局所デリバリーだ。具体的には、(1)hydrogel(ハイドロゲル)による局所滞留と徐放、(2)微粒子・ナノ粒子による時間プロファイル制御、(3)マイクロニードルなどの侵襲最小化デバイス、(4)ECM様足場による力学シグナル付与、が重要な構成要素となる。研究者の設計言語としては、「どの経路を触るか」より先に「どの空間スケールと時間スケールで触るか」を決める必要がある。全身曝露でWnt/Notch/transforming growth factor beta(TGF-β)を触るのは危険だが、損傷局所で数日だけ“再生相を延ばす”程度なら、腫瘍化リスクを現実的に抑えうる。
11. 実験系の組み立て:in vivo幹細胞“増殖”を証明するには系統学が要る
研究として「体内で幹細胞が増えた」を主張するなら、単に増殖マーカー(Ki-67、BrdU/EdU)を示すだけでは弱い。最低限、(A)lineage tracing(系譜追跡)、(B)clonal analysis(クローン解析)、(C)long-term repopulation assay(長期再構成能)に相当する機能評価、(D)ニッチ側のトランスクリプトーム・空間解析(spatial transcriptomics等)を統合する必要がある。造血系では移植再構成が強力な機能アッセイになるが、非造血組織ではオルガノイド形成能や損傷モデルでの機能回復を、クローン追跡と結びつける設計が望ましい。
臨床側へ翻訳する場合は、画像、機能、液性バイオマーカーに落とし込む必要があるが、研究段階では「幹細胞数」よりも「幹細胞の自己複製様式(対称/非対称分裂)」「分化の偏り」「枯渇徴候」を評価軸に入れるべきだ。
12. 今後の方向性:万能の“幹細胞増殖薬”ではなく、文脈特異的な再生スイッチだ
要するに、体内で幹細胞を増殖させる再生医療は、単一因子で幹細胞を増やす発想から、損傷文脈に応じてニッチネットワークを短時間だけ再配線する発想へ移行している。臨床で確立したのは、G-CSFやplerixaforに代表されるHSPC動員であり、CXCL12–CXCR4軸の“保持解除”という明確なメカニズムがある。
一方、非造血組織での増殖誘導は、Wnt–RSPO–LGR軸や部分的リプログラミングのように強力な再生スイッチが見え始めた反面、腫瘍化・線維化・機能破綻の距離が近い。

研究者・医師が持つべき実装原理は、(1)局所・短期・可逆、(2)炎症相の時間窓設計、(3)ニッチ(血管・神経・免疫・間質)を含めた系統的評価、(4)CHIPを含む長期安全性科学の組み込み、である。
この4点を満たして初めて、「体内で幹細胞を増殖させる」という事が科学的に検証可能な仮説として成立するのだ。
免疫系でもこの幹細胞系にしても計測自体が困難で、臨床的には何を以て「増殖、亢進」しているかの判定で苦慮するのが常だ。特に幹細胞系は「症状の軽減」で判断されることが多いと思う。若返りなんかは、以前話した「生物的年齢」を測るエピクロック検査などが出てきたので分かりやすくなると思うが。とにかく近い将来、体外培養を用いず、薬だけで体内の幹細胞が増殖し再生医療が行えるようになる日が来る事に期待したいと思う。