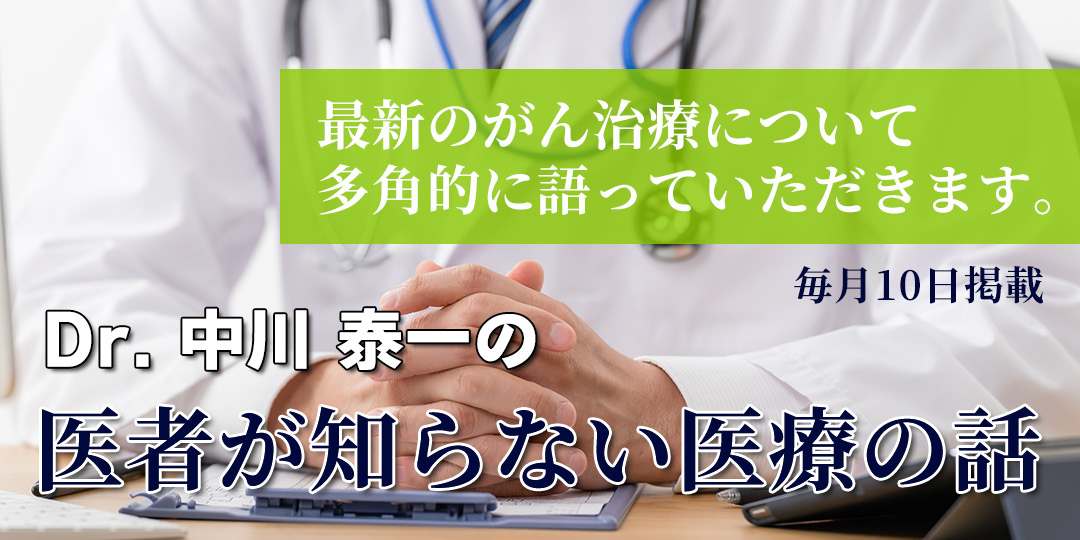今連載も何と100回目になる。色々再生医療についても述べてきたが、臍帯血などの人体より採取した幹細胞を直接投与する方式。ないし、脂肪や骨髄などから採取した幹細胞を培養して投与する方式だ。再生医療法以後に「上清液」が流行ってきたが、幹細胞の培養はこの辺りから盛んになってきとと思われる。それ以前は、臍帯血などの幹細胞をバンキングヅル方式であった。私のCPCde少ない幹細胞の検体から複数回治療に使えるように、臍帯血の培養を試みていたが、再生医療法以後、他家移植が事実上の禁止になったので、臍帯血移植も白血病治療以外は使えなくなった。皮肉なことに、「幹細胞」の代わりに「上清液」が使われる様になった為に幹細胞の培養が進んだのだが。これらの究極系が「Induced Pluripotent Stem cell(iPS)(人工多能性幹細胞)」だと思うが、この件は後日。ちなみに、「iPS」の「i」だけ小文字になってる。(気がついてましたか?)この理由は開発者の山中伸弥教授が、「iPodのように広く普及してほしい。」という願いを込めて「i」だけを小文字にしたそうな。
前置きが長くなったが、今回は体内で幹細胞を増殖させる再生医療の研究最前線。体外で「幹細胞」を培養して増殖する方法だ。
「体内で幹細胞を増殖させる」再生医療とは、患者から細胞を取り出して培養・加工して戻す ex vivo 型(細胞加工物ベース)とは異なり、内在性の幹細胞(あるいは前駆細胞)を生体内で動員・増殖・分化誘導し、同時にニッチ環境を再設計して組織再生を引き出すアプローチの総称だ。研究者の視点では、(1)幹細胞プールの量的操作(増殖・拡大)、(2)空間的操作(動員・ホーミング・局在)、(3)時間的操作(損傷修復の相転移:炎症→増殖→成熟のタイミング制御)、(4)系の操作(免疫・血管・神経・間質・ extracellular matrix(ECM) の統合制御)を同時に扱う“システム介入”だと捉えるのが適切だ。以下、箇条書き的に書くと。
1. まず「増殖」と「動員」を分けて理解する必要がある。
「増殖」とは幹細胞を増やすことであり、「動員」とは幹細胞を増やすのではなく、ある場所に幹細胞を誘導、集中させることだ。
臨床で確立したモデルは、実は「増殖」よりも「動員」が中心だ。動員の代表が造血幹細胞 hematopoietic stem cell(HSC)と造血幹・前駆細胞 hematopoietic stem and progenitor cell(HSPC)の動員であり、granulocyte colony-stimulating factor(G-CSF)で骨髄から末梢血へHSPCを動員する手法が標準となっている。ここで重要なのは、G-CSFは単純にHSCを“増やす”のではなく、骨髄ニッチの保持機構を崩し、HSPCの局在を変えることで可用性を上げる点だ。G-CSFや化学療法による動員において、C-X-C motif chemokine ligand 12(CXCL12)— C-X-C chemokine receptor type 4(CXCR4)軸の攪乱が中核機序として位置づけられている。
したがって「in vivo 幹細胞増殖」を議論する際は、(A)真のプール拡大(自己複製の増加、枯渇リスクを伴う)と、(B)局在変化(動員・遊走・ホーミング)を峻別し、どちらを狙っている介入なのかを明示する必要がある。
2. 骨髄ニッチは「細胞の集合」ではなく「動的ネットワーク」
造血系はin vivo 操作の教科書であり、ニッチ概念の精度も高い。骨髄では、mesenchymal stromal cell(MSC)系、血管内皮、骨芽細胞系、perivascular cell、神経(特に交感神経)、免疫細胞が相互依存ネットワークを形成し、HSCの休眠 quiescence と活性化をスイッチングする。
たとえば、骨髄のCXCL12-abundant reticular cell(CAR cell)はCXCL12供給源としてHSC保持に関与し、炎症刺激下ではinterleukin-6(IL-6)など「非常時造血」シグナルの供給源にもなり得る。
この「ニッチの可塑性」こそが、体内で幹細胞を増やす再生医療の本体である。幹細胞を直接いじるのではなく、支持細胞・血管・神経・免疫の状態を変えることで、幹細胞の運命(自己複製/分化/遊走)を間接的に変えるという設計が中心になる。
3. CXCL12–CXCR4軸の遮断は「局在の操作」を最も直接に実現する。
CXCL12–CXCR4保持軸を直接遮断する薬理として、CXCR4 antagonist である plerixafor(臨床ではAMD3100としても知られる)がある。PlerixaforはG-CSF単独で動員不良となる症例に併用され、末梢血CD34陽性細胞の動員を増強する。
研究者の方の目線では、これは「幹細胞増殖」ではなく「ホーミング/保持の結合を切る」操作だが、in vivoで幹細胞動態を制御できることを臨床で証明した代表例だ。近年はmotixafortideなど新規CXCR4阻害薬のレビューも出ており、動員戦略は多様化している。
4. ニッチ操作の臨床的プローブとしての parathyroid hormone(PTH)
幹細胞の体内増殖・動員を「ニッチ操作」として理解するのに便利な臨床例が、parathyroid hormone(PTH)1-34(teriparatide)だ。閉経後女性においてteriparatide投与で末梢血中のHSCが増加した報告があり、骨芽細胞系・骨髄微小環境を介したHSC動態変化の概念を支持する。
ここから得られる設計原理は、幹細胞は“受動的に増やす対象”ではなく、ニッチ側の代謝・力学・分泌プロファイルに強く制約されるという点だ。再生医療をin vivoで成立させるには、標的組織のニッチ(血管・間質・神経・免疫)の再配線を先に設計すべきである。
5. 「生着効率」を上げるin vivo介入: dipeptidyl peptidase-4(DPP-4)阻害
HSC領域では「増殖」よりも「生着」がボトルネックになる場面が多い。臍帯血移植 umbilical cord blood transplantation(UCBT)では、細胞数制約により生着遅延が問題となるが、dipeptidyl peptidase-4(DPP-4, CD26)阻害がCXCL12などのケモカイン/サイトカイン活性を保護し、生着を改善し得るという前臨床知見があり、sitagliptinを用いた in vivo DPP-4 inhibition の試験が行われている。
この系も「幹細胞を増やす」というより、ホーミング・生着の効率を上げることで機能的幹細胞量を稼ぐ発想だ。in vivo再生医療では、実効性を規定するのはしばしば「増殖速度」ではなく「到達・定着・生存」だという点が重要だ。
6. 炎症は幹細胞増殖のアクセルでもあり、変異クローン選択のドライバーでもある。
in vivoで幹細胞を活性化する設計は炎症制御と不可分だ。炎症は非常時造血 emergency hematopoiesis を駆動し、HSCの休眠解除、ミエロイド偏位、自己複製様式の変化を引き起こす。 しかし同時に、慢性炎症はHSCの“inflamm-aging”を促進し、clonal hematopoiesis of indeterminate potential(CHIP)のような前腫瘍状態における変異クローンの選択と拡大に関与し得る。
したがって研究設計上は、増殖刺激を強めるほど「腫瘍化リスクが上がる」という一般論に加えて、既存のクローン構造(加齢・喫煙・治療歴で変化する)と炎症環境が、増殖刺激に対する応答を歪める可能性を想定すべきだ。とくに造血系はクローン追跡が可能であるため、in vivo再生介入の安全性科学(長期追跡、クローン競合、炎症環境)を検討する“試験場”として価値が高い。
次回に続く。