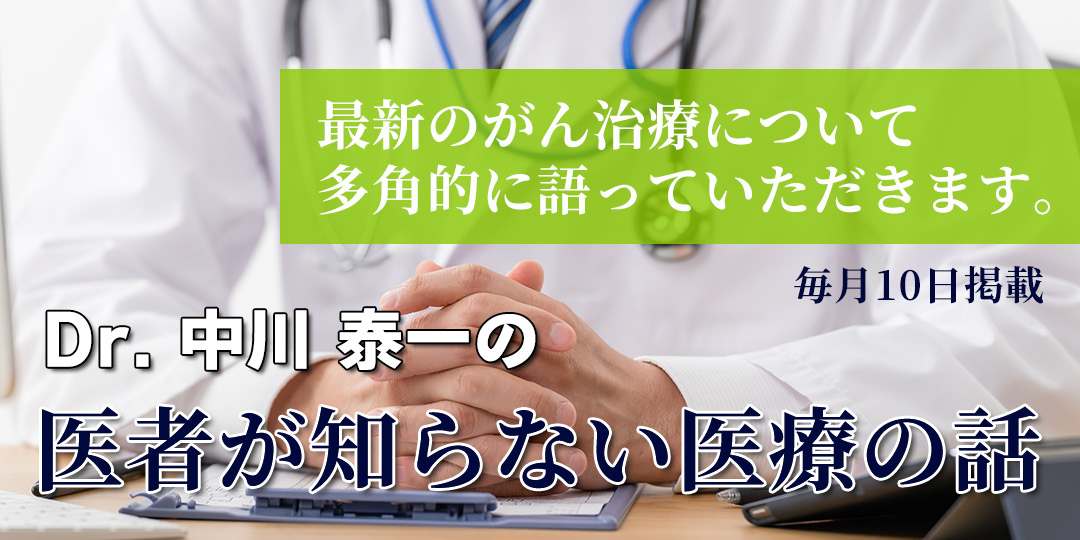最近やっと、海外の企業や研究者たちもマクロファージの事に関心を持ってきてくれたようだ。以前からの知り合いの企業や研究者の方は知ってくれていたのだが、ちょうど同じ時期に中国の多くの病院を傘下に持つ研究機関と台湾のバイオ企業たちに「わかりやすく」説明してくれと言う事だった為、スライドを作った。そう言えば、マクロファージとTreg、ミトコンドリア、腸内フローラの相関についてまとめて話した事がなかったかなと思う。部分的には何度か話したと思うけど。特にマクロファージがM1、M2のみならずスペクトラムを形成しており、その間に多様なマクロファージが存在する事。もう一つ抗癌作用については腫瘍関連マクロファージ(TAM)とTreg の関係からNK細胞などの抑制に働いて、癌を惹起する作用しかないとおもわれている節があり、この手の質問を受けた事もあった。この辺りの誤解も解いておこうと思う。
マクロファージ活性化と制御性T細胞・ミトコンドリアの免疫調整への役割
ご存知のように、マクロファージは自然免疫の主役であり、全身の免疫応答の制御において中心的な役割を果たす。さらに単なる異物の貪食・除去にとどまらず、多様なサイトカインを分泌することで、リンパ球をはじめとする他の免疫細胞の機能を調節する。
とりわけ、マクロファージの活性化状態は制御性T細胞(Treg)の誘導および機能維持に強く影響する。腸管のマクロファージは抗炎症性サイトカインであるIL-10やTGF-βを分泌し、Treg細胞の拡大と維持を促進することで粘膜免疫の恒常性に寄与する。一方、Treg細胞もIL-10などを産生してマクロファージの過剰な炎症反応を抑制し、免疫応答の暴走を防止する。
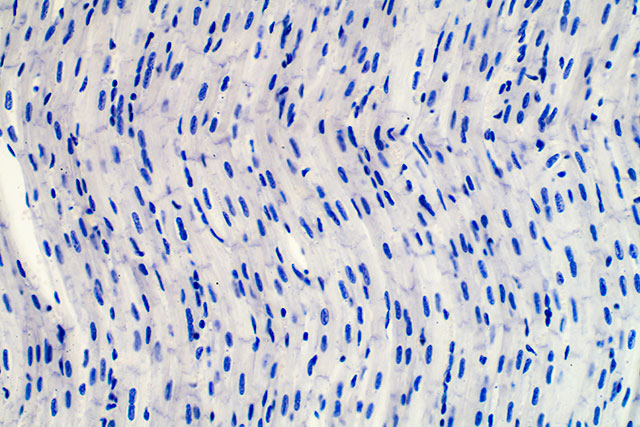
免疫細胞の機能発揮には、細胞内の代謝状態、特にミトコンドリアの活動が深く関与する。Treg細胞は脂肪酸のβ酸化および酸化的リン酸化(OXPHOS)に依存する代謝プロファイルを有し、ミトコンドリア代謝の活性化が転写因子FoxP3の安定化と抑制機能の維持に不可欠であることが示されている。マクロファージもまた、活性化様式に応じて代謝経路を切り替える。古典的活性型(M1)では解糖系に依存し、代替的活性型(M2)では脂肪酸酸化を含むミトコンドリア呼吸に依存する。
このように、マクロファージの活性化とTreg細胞・ミトコンドリア代謝との相互作用は、免疫恒常性の維持および応答制御において密接に関連している。
そこで以下に、腸管マクロファージと腸内フローラの相互作用による免疫調整の仕組みを詳述し、癌免疫(腫瘍微小環境における免疫抑制性マクロファージの役割)および自己免疫疾患(炎症性サイトカイン制御とTregの関係)におけるマクロファージとTregの関与を概説する。さらに、M1/M2の二分類を超えたマクロファージの多様な役割つまり代謝調節、神経免疫制御、全身の免疫ネットワークへの波及を解説して行こうと思う。
腸管マクロファージと腸内フローラによる免疫調整
腸管には体内最大級のマクロファージ集団が存在し、腸内フローラとの絶え間ない相互作用を通じて免疫恒常性の維持に貢献している。腸管マクロファージは上皮直下の固有層に位置し、樹状突起を上皮越しに伸ばすことで消化管内の抗原や微生物を捕捉し、常在菌と病原体を識別している。捕捉された微生物に対しては貪食や殺菌を行う一方、損傷上皮の残骸処理(エフェロサイトーシス)やIL-10の産生を通じて過剰な炎症反応を抑制している。
実際、マウスにおいてマクロファージ上のIL-10受容体を欠損させると腸管に制御不能な炎症が生じ、重篤な大腸炎を引き起こすことが報告されている。ヒトにおいてもIL-10受容体の先天的欠損は若年性の難治性炎症性腸疾患を発症させることが知られており、マクロファージによるIL-10シグナル伝達を介した炎症制御が腸管免疫において不可欠な要素であることを示している。
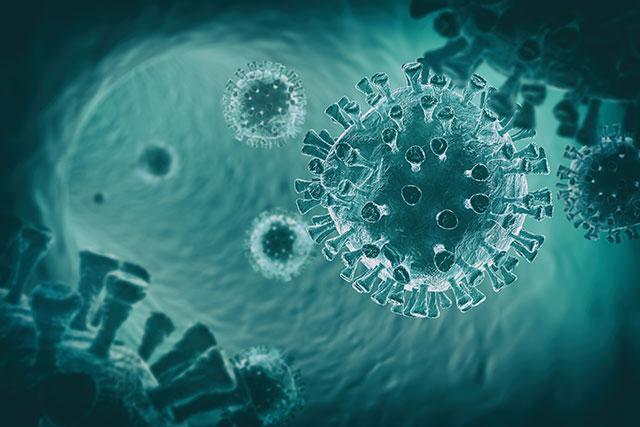
また、腸内フローラはマクロファージの性質に大きく影響を与えている。健常な共生細菌叢からの刺激を受けたマクロファージはCX3CR1高発現の成熟型へと分化し、IL-10を高産生する免疫寛容的な性質を獲得する。一方、腸内フローラが抗生物質などにより枯渇すると、腸管マクロファージのターンオーバーが著しく低下し、局所免疫応答にも変調をきたす。また、病原菌感染下では、本来免疫寛容的であったマクロファージが樹状細胞様の性質を示し、抗原を携えて腸間膜リンパ節に移動する現象が観察されている。
さらに、腸管マクロファージと腸神経系との相互作用も明らかとなっている。粘膜下層に位置するマクロファージは、腸管神経叢と呼ばれる神経ネットワークと双方向のクロストークを行っており、マクロファージ由来のBMP2が腸神経に作用して神経ペプチドの分泌を促進し、応答として神経由来のCSF1が再びマクロファージの生存やBMP2産生を支えるというフィードバック機構が存在する。
寄生虫感染時には腸神経がニューロメジンU(NMU)を分泌し、これがILC2(2型自然リンパ球)を活性化しIL-13を分泌させる。このIL-13が腸管マクロファージをM2様へと誘導し、組織修復やTreg細胞の誘導に寄与する。腸内フローラ由来の代謝産物も免疫調整に関与しており、短鎖脂肪酸(SCFA)はTreg細胞の分化促進や抗炎症環境の形成に寄与する。これらの知見は、腸管マクロファージと腸内フローラの相互作用が免疫恒常性の維持において極めて重要であることを示している。
次回はいよいよマクロファージとTregの関係について。