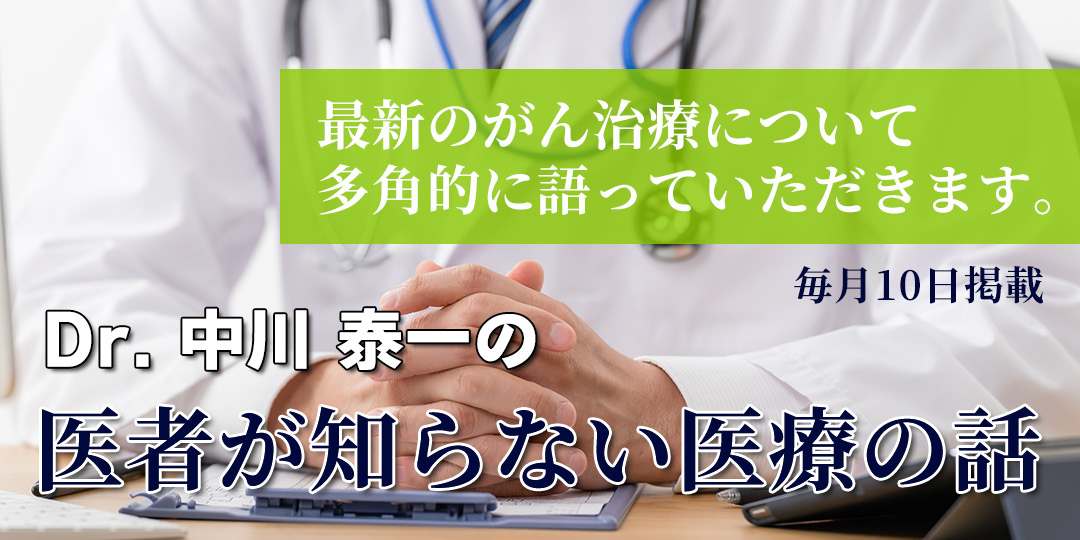がんと細菌の関係について
以前癌治療と抗生物質について触れた。今回は、「腸内フローラ」も絡めた関係を最新の知見を含めて考えてみたい。
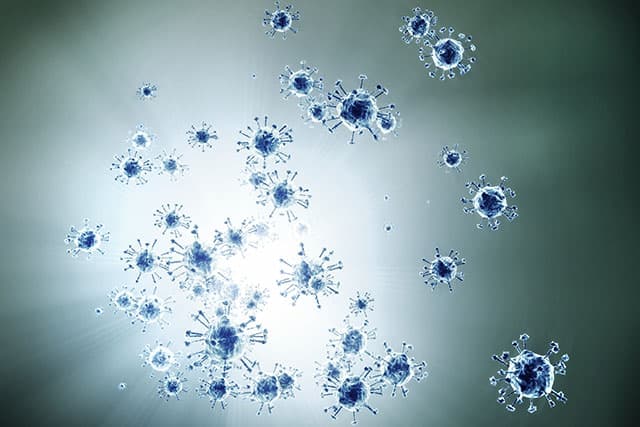
近年、癌組織内に細菌が恒常的に存在することが示されている。細菌は腫瘍表面だけではなく、癌細胞内や腫瘍随伴免疫細胞内にも検出されることが多い。そして、腫瘍種ごとに構成が異なる「腫瘍内マイクロバイオータ」という概念が受け入れられつつある。これらの細菌は炎症や代謝、免疫応答、薬剤感受性に影響するとされる。
細菌の主な侵入経路は呼吸器が多いと思われる。一般的には感染症の多くは呼吸器から侵入する印象がある。いわゆる「風邪」などは最も日常的な感染症で、よく聞くところの「空気感染」「飛沫感染」などで感染が広がるからだ。ところが、腫瘍内細菌は「こんなところにいるはずのない菌」と表現されたりする。なんと、その主な供給源は口腔内と腸内の細菌叢だ。口腔からの一過性菌血症や腸管バリア破綻を介して腫瘍に到達する経路が想定されている。確かに腫瘍内は低酸素・酸性・栄養枯渇など特殊環境が支配的で、嫌気性菌や通性嫌気性菌にとっては居心地の良い環境だ。
そこで癌治療に対して「抗生剤の有効性」という概念が出来上がってきたわけだ。
抗生剤の基本的な位置づけ

抗生剤の癌治療に対する位置づけは二つに分かれる。まず第一が「原因除去型」だ。例えば、H. pylori感染が主要因である胃MALTリンパ腫の早期例では、除菌療法がそのまま腫瘍治療となりえる。そして、もう一つが「耐性解除・増感型」だ。腫瘍内細菌が化学療法や放射線、免疫療法の効果を妨げる場合に、短期・選択的な抗生剤で「邪魔をする菌」を減圧し、主治療の効果を最大化するという発想だ。例えば、大腸がんでのFusobacterium nucleatum高負荷に対するメトロニダゾール短期併用や、膵がんでのゲムシタビン不活化に関わる菌に対するフルオロキノロン短期併用などが代表例だ。
一方使用に注意しなければならない場合もある。抗がん剤などに比べ、抗生剤は副作用が少ない印象だが、治療の邪魔になる場合もある。主な例が、免疫チェックポイント阻害薬(ICI)導入の前後の広域抗生剤投与だ。これらは腸内叢を破壊して、治療成績が悪化し得るので、原則として避けるべきだ。必要な場合でも狭域・短期・デエスカレーションを徹底するべきだ。
このように腸内細菌叢(腸内フローラ)は単に免疫能向上に関与しているだけでなく、もっと直接的に癌の発生や転移に関与することが示されている。
腸内フローラ移植の役割

腸内フローラ移植はご存知のように、ドナー腸内叢を患者に移植し、受け手の腸内叢を機能的に置換する治療だ。腸管マクロファージとの連携によって免疫系を調整する。さらに短鎖脂肪酸、二次胆汁酸、トリプトファン代謝物などの代謝地形を変化させ、樹状細胞、CD8T細胞、Treg、マクロファージ極性、サイトカイン環境を再調律する。そして、腫瘍微小環境の免疫が抗腫瘍方向へ作用する。
これらの作用により、直接的な抗癌作用に加え、抗PD-1抵抗性メラノーマで腸内フローラ移植後に抗PD-1を再導入すると、抗PD-1効果が再出現する症例があることが報告されている。この現象は、消化器癌を含む固形癌でも有望例が報告されつつある一方、陰性例もあり、ドナー選定やタイミング、前処置が成否を分けると考えられている。
ただ、現状では癌治療において、腸内フローラ移植単独では癌が大きく縮小することは限定的で、主として免疫療法や化学療法と併用することで、その効果を回復・増強する役割と理解するのが良さそうだ。ただ、今後さらに腸内ふろーらの癌に対する関与が明らかになっていくだろうから、現状でも重要な癌治療法であることに変わりないと思っている。 次回はもっと具体的な手法について考えてみたい。