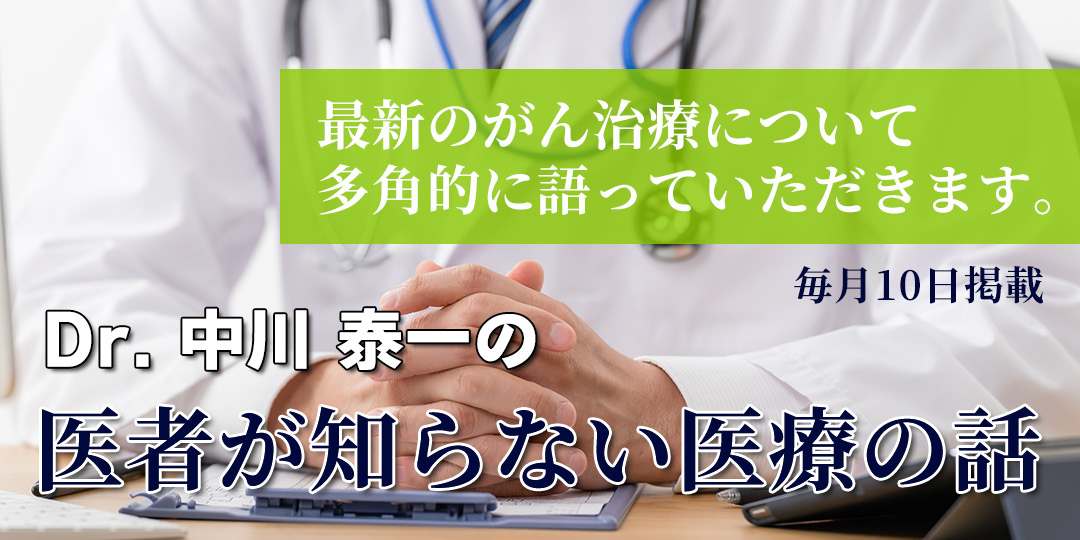目次
今回は、それぞれのエピジェネティッククロック(Epigenetic Clock)の技術的なお話の残りと、最皆さんが最も関心がおありと思う実際臨床での応用について述べたいと思う。
4. 測定技術と解析手法
エピジェネティッククロックの構築には、主に以下のようなメチル化解析法が用いられる:
- Illumina Infinium HumanMethylation450 BeadChip
- Illumina EPIC Methylation BeadChip(850K)
- Whole-genome bisulfite sequencing(WGBS)
CpGサイトのメチル化率(β値)を取得し、既存のモデル(Horvath, Hannumなど)に当てはめて解析するか、カスタムアルゴリズムを構築する。解析にはRやPythonなどでの機械学習・統計処理が必要であり、バッチ効果やノイズの補正も重要なステップとなる。
5. 臨床応用と研究例
5.1 アンチエイジング医学
これが最も関心のある事柄と思う。実際、「老化は病気だ!」とまで言われるようになっているのに、その基準である「老化の度合い」を測るすべがなかったからだ。現実的にも、身の回りを見回せば、同じ年代でも10歳若く見える方もおられるし、逆に10歳老けていえる方もおられるだろう。もちろんこれは外観での部分が多く、臓器などの肝心な「年齢」は色々と検査しないと分からないが。それにしても、髪の毛が薄かったり、白髪が多いとか小皺があると言う程度で、外観の印象はガラッと変わる。だからこそ「美容医療」が盛んなわけだが。また、「気は若い」が、身体はくたびれてる人もいる。こんな訳で、実際の身体の年齢、つまり「生物学的年齢」と言う指標が重要になってくるわけだ。メチル化年齢と実年齢の差(Age Acceleration)が、運動、断食、NMN投与、サプリメント、睡眠、瞑想などのライフスタイル介入によってどのように変化するかを測定する研究が進んでいる。例えば、短期的な菜食中心の食事と運動介入で平均2~3歳のメチル化年齢低下が観察された報告もある。さらに、今言われている、サーチュイン遺伝子の活性や、老化細胞の除去などの薬剤を服用しての結果がどうなるか楽しみだけど。既に効果ありとされてる薬剤の組み合わせだから、効果無かったら大変なんだけれど、まあ何事もやってみないと分からないからね。生活習慣などの要因も考慮しないといけないしね。
5.2 疾患との関連
PhenoAgeやGrimAgeは、がんや心血管疾患、2型糖尿病、認知症の発症予測において有用とされる。特に慢性炎症(Inflammaging)との相関が高く、慢性疾患のリスク層別化に活用可能である。やはり、この慢性炎症は糖化と並んで諸悪の根源のような物だから、これの評価が確立すると色々な疾患に対する予防や、治療に大いに貢献すると思われる。
5.3 再生医療および細胞評価
細胞移植におけるドナー細胞の品質評価指標として、エピジェネティック年齢が活用されつつある。例えば、MSCの老化度評価やiPS細胞のリプログラミング後の若返り評価に応用されている。これも、先述の老化に対する評価と似たような括りになるが、再生医療自体が「若返り」にも効果があると期待されている以上(実際、脂肪肝細胞なんかの治療を受ける人、中国人が多いのだが、この人達は大体、美容、若返り目的)必要な指標だと思う。
6. 限界と課題
- 組織特異性:あるモデルが他の組織に適用可能かどうかは明確でない場合がある。
- 病的状態の影響:炎症や腫瘍などの疾患状態がメチル化年齢にどの程度影響を与えるか、慎重な解釈が必要。
- 解釈の困難性:メチル化年齢が実年齢より高いことが、必ずしも疾患やリスクを意味するわけではない。補助的な指標としての活用が望ましい。
7. 商用化と社会実装
近年、多数の企業がDNAメチル化に基づいたエピジェネティッククロック検査を提供している(例:TruMe, EpiAge, myDNAge, EpiClockなど)。ただ価格は一般的なもので1回5~10万円程度だが、研究レベルになると1回20万円以上かかる。データーを取るための定期的なモニタリングや治療前後の変化を評価する目的での導入にはコストがかかり、前後で50万円弱のコストを患者さんが負担してれるか問題だ。統計取るには最低一群6人必要で、脱落など考えたら8~10人は欲しい。対照群を一つとしても20人ほどは必要になる。1,000万円ですよ!検査代だけで。共同研究だから検査代ぐらいタダでやってくれないかね。直ぐに利益に結びつく訳でもないし。貧乏医療法人には辛いね!
8. 今後の展望
- マルチオミクス(トランスクリプトーム、プロテオームなど)との統合により、より包括的な老化評価モデルの開発が進む。
- AIやディープラーニングを活用した、予測精度のさらなる向上。
- 唾液や尿など非侵襲的検体を用いた解析法の実用化。
- 保険診療や個別化予防プログラムとの連携による社会実装。
まあ、このような明るい未来はあるが、あくまで自由診療である「老化防止」や「若返り」の治療との組み合わせで無いと意味がない事。それに伴うこれらの検査や研究費をどこから捻出するかが、現実的には大きな問題になると思う。