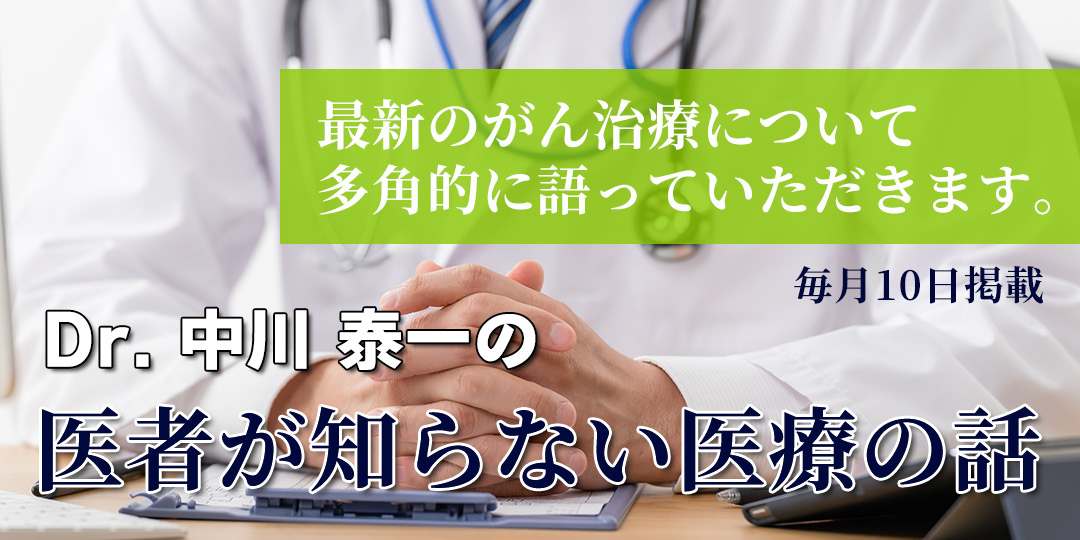マクロファージの働きは非常に多彩で色々面白い。どれから話題にしようかと思うのだが。
最近、「腸内フローラ」がウケている。いや、私のところの話だ。元々は腸内細菌はマクロファージと密接に関係しており免疫系の調整に深く関わっているのは聞かれたことがあると思う。まぁその関係でウチでも「腸内フローラ移植」を行なっているのだが、大阪にはいわゆる「難病」であるアトピーや自己免疫性疾患、リッキガッター症候群などの「医療難民」の方々が全国から来られているのだが、東京では便秘などの腸の不調や美容系、特に「痩せ菌」目当ての方々が多いのだ。免疫や再生医療は癌や難病だけでなく、いわゆるアンチエイジングや美容系にも高い効果がある。元々、私は末期癌の治療には栄養を含む全身管理と癌が生えにくい体にする体質改善は不可欠と主張している。見えている癌だけ排除しても「完治」とは言えない。画像で見つかる最小の1cmの癌でさえ既に「末期癌」だ。まあこの話は後程ゆっくりと。
つまり、末期癌や難病の治療と美容系とやる事は「同じ」なのだ。よって、美容系の「治療」?も行なっている。目的は美容でも、腸内細菌やマクロファージはじめ免疫細胞は、人様の「目的」なんか関係なくあらゆる仕事を行う。免疫の癌治療時に一応「副作用」として「お肌が綺麗になったり、血行が改善して糖尿の痺れが取れたり、視界が明るくなったりしますが・・・」と説明するのだが、今までただの一人もそれで、癌治療を拒否した方はおられない。あたりまえだが・・・。
閑話休題、
腸には腸内細菌叢が存在し、人の色々な消化活動をアウトソーシングしてもらっていることは以前触れた。細菌を認識すると素早く作動する自然免疫細胞が、腸管粘膜組織では、腸内細菌を排除しないだけでなく、細菌に反応して炎症反応を起こす事がない。これは自然免疫細胞の活性を抑えるIL-10(インターロイキン10)を自ら産生しているからとわかってきている。そして、この状態が崩れて細菌に反応してしまうとクローン病(CD)および潰瘍性大腸炎(UC)などの炎症性腸疾患(IBD)を発症してしまう。
マクロファージは、表現型をそれらの環境によって変化させる。マクロファージと同様に、「腸マクロファージ」は分化した単球であり構造が非常に類似しているが、「腸マクロファージ」は特定の機能を進化させた。どういうことかというと、腸マクロファージは腸内の腸内細菌叢と共存しなければならない。
これは、腸マクロファージは本来免疫的に排除しなければならないはずの腸内細菌を排除してはいけないということだ。このために、腸内マクロファージは他のマクロファージと異なり、炎症応答を誘導しない。組織マクロファージはIL-1、IL-6およびTNF-αなどの様々な炎症性サイトカインを放出するが、腸マクロファージは炎症性サイトカインを産生または分泌しない。
この変化は、腸マクロファージを取り囲む環境によって直接引き起こされる。腸マクロファージ周囲の腸上皮細胞は、炎症性マクロファージから非炎症性マクロファージへの変化を誘導するTGF-βを放出する。
面白いことに、炎症応答は腸マクロファージにおいて下方制御されているにもかかわらず、食作用は依然として行われている。腸内マクロファージは細菌、S.typhimuriumおよびE.coliを効果的に貪食することができるので貪食効率の低下はないが、食作用後もサイトカインを放出しない。
このように健常な腸では、腸マクロファージは腸内の炎症応答を制限するが、疾患状態では、腸マクロファージ数および多様性が変化する。そして、腸内細菌叢を攻撃することにより、クローン病(CD)および潰瘍性大腸炎(UC)などの炎症性腸疾患(IBD)の腸および疾患の症状をもたらす。
また、腸マクロファージおよび腸内細菌叢は各種のアレルギー疾患にも関与している。
この30年間で,抗生物質の発達により先進国の腸管感染症による乳幼児死亡率は激減した。その一方で乳幼児に形成される腸内フローラ構成も著しく変異したことが報告されている。
胎児や新生児のT細胞は明らかにTh2優勢(Th1Th2)へとシフトすることが免疫防御機能の正常な発達に重要と考えられている。これが十分でないと,いつまでもTh2優勢が持続することとなり,その結果IgE抗体を主体としたアレルギー・アトピー性疾患発症へとつながるのだ。
この続きは次回に。