話題沸騰!数々の人気番組に出演している医師たちが語る
「キャリア」「信念」「未来」そのすべてに迫るインタビュー!
どのようにしてスキルを高め、逆境を乗り越えてきたのか?
日常の葛藤、医師としての信条、そして描く未来のビジョンとは――。

【出演番組一部抜粋】
NHKプロフェッショナル仕事の流儀・世界一受けたい授業・たけしの家庭の医学・主治医がみつかる診療所・NHKあさイチ
今回は【徳島大学病院 病院長】西良浩一先生のインタビューです!
なぜ整形外科医になったのか。スポーツDr.になった理由は?
どのようにして数々の世界初手術をやってきたのかなど語っていただきました――。
第3回「私の問診は教科書には載っておらず、自分で確立した方法です」をお話しいただきます。
プロフィール
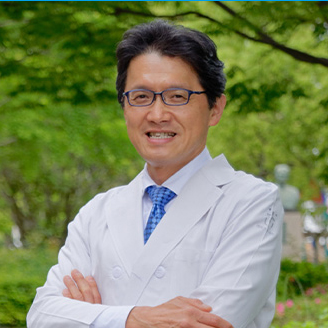
| 名 前 | 西良(さいりょう )浩一(こういち) |
|---|---|
| 病院名 | 徳島大学病院運動機能外科学 |
| 所 属 | 整形外科 |
| 資 格 |
|
| 経 歴 |
|
|---|
ー帰国後はどのような仕事をしてこられたのですか。
最初はスポーツドクターとしてのキャリアをスタートしました。
ただ、その当時は地元の子どもを診ることが中心でした。具体的な仕事といえば、コルセットの処方や腹筋、背筋、ストレッチの指導といったもので、本当に地味なものでしたね。たまにヘルニアの患者さんがいましたが、基本的には手術をせずにリハビリで治療するという形でした。改めて考えると、地味な分野だったと思います。
その後、徐々に立場が上がるにつれて、スポーツ腰痛だけでなく、一般的な脊椎の病気も担当するようになりました。例えば、ヘルニアや狭窄症といった大人の腰痛や首の疾患など、脊椎全体を診る機会が増えていったんです。子どもの腰痛は症状が腰だけに現れることが多いのが特徴です。一方で、大人の腰痛は足のしびれや痛みが伴うことが多く、ヘルニアの診断などはMRIで比較的簡単です。
しかし、部活動中の子どもの腰痛は画像検査に何も映らないことがよくありました。筋肉痛か、肉離れか、あるいは腰の関節を捻挫したのか、診断が非常に難しかったんです。「痛みの原因が分からなければ治療できない」という状況の中、少しでも原因を探り当てることに全力を注いでいました。
そういった経験を経て、大人の腰痛を診るようになったときには診断が非常に簡単だと感じました。他院で「原因不明」とされた症状も、子どもの腰痛を必死で診ていた経験があったおかげでスムーズに診断できたんです。
今では日本中から「謎」と言われる患者さんが来られますが、子どもの腰痛を突き詰めてきた経験があるからこそ、原因を見つけることができています。そのやり方に基づけば、私にとって「謎」になるケースはほとんどないんです。
ー腰痛診断と問診の重要性について、お聞かせください。
子どもの腰痛を診るのは本当に難しいんですよ。子どもは「痛い」しか言ってくれないですからね。私としては「どこが痛い」「どう痛いの」などと聞きながら、何とか原因を探っていくしかありません。
腰痛を火事に例えると分かりやすいのですが、消防署に電話がかかってきて、「火事です。火を消してください」と言われたら、「どこが火事なの」と質問したくなりますが、向こうは「火事としか言えません」となります。それでは火事の場所も分かりませんし、消化活動もできません。
腰痛もそれと一緒で、「腰が痛い」と言われただけでは分からないです。そのため、丁寧に聞いていくしかありません。「咳やくしゃみをすると響く?」「朝起きたときは痛い?」「顔を洗うときや靴下を履くときは痛い?」「地べたに座るとどう?」みたいに、一つ一つ聞きながら情報を集めていきます。火事の場所を電話で聞くのと似ています。「電車の色は黄色?黄緑?」「犬の銅像が近くにある?」と聞きながら、最終的に「あ、渋谷駅が火事ですね」とたどり着く感じです。
腰痛も同じで、色々と質問をしながら細かいところを突き詰めていくと、「問診の段階で、これは多分、4番と5番の間の椎間板が原因だな」などと、少しずつ見えてきます。いきなりMRIを撮っても分からないことが多いのですが、問診で十分に情報を集めておけば、そのポイントが頭にしっかり入っているので、MRIを見たときに「ああ、これだ」と分かるんですよ。
私はそうやって、患者さんの症状を掘り下げていきます。そして「これは関節炎かな」「これは椎間板が原因だな」と判断していきます。それを繰り返していくうちに原因が分かるようになってきます。
ーそれは先生が開発された方法なのですね。
私の問診の仕方は教科書には載っておらず、完全に自分で確立した方法です。だから、今も国内から6人の医師が私のところに留学に来ており、外来で私の質問の仕方を見聞きしながら学んでいます。
最初は「この人は何を聞いているんだろう」という顔をしていますが、後半になると慣れてきて、私が問診をしていると後ろから「これはモディックじゃないですか」「椎間板が原因ですね」といった具合に、問診だけで結論を導き出せるようになります。
私の問診を聞いていると、周りの人たちは「西良先生はここを疑いながら話を進めているんだな」と分かるようになってくるんです。MRIは航空写真に似ています。
例えば「火事です」という電話を受けて、「分かりました。ヘリを飛ばそう」となり、東京都23区全体をヘリから見渡してもどこが火事かなんて分かるわけがありません。MRIも同様で、縦切り、横切りと様々な多くの画像がある中で、「どこを見ればいいのだろうか?」という状態になります。
しかし、私は問診で「この症状は椎間板が原因だな」と目星をつけます。そして「特に4番と5番の間が怪しいな」という前提でMRIを見ると、狙ったところが見えてくるんです。これは渋谷駅を探すようなもので、ヘリから東京都を見渡しても渋谷駅の特定はできませんが、「ハチ公前を探そう」と意識してじっくり見れば、そこが見つかるんです。
私は「謎解きチャート」という独自の方法を作り上げており、本を出しています。その本を購入して、このチャートを見た患者さんが「私はモディックだと思います」と相談に来られることもありますし、「ほかの先生にこのチャートを見せても取り合ってくれないけれど、私の症状はこれに該当するのではないでしょうか」と真剣に話してくれることもあります。
こういった問診の積み重ねで、診断がより正確になり、患者さんとしっかり向き合うことができていると思っています。



