話題沸騰!数々の人気番組に出演している医師たちが語る
「キャリア」「信念」「未来」そのすべてに迫るインタビュー!
どのようにしてスキルを高め、逆境を乗り越えてきたのか?
日常の葛藤、医師としての信条、そして描く未来のビジョンとは――。

【出演番組一部抜粋】
プロフェッショナル 仕事の流儀、NHKスペシャル
今回のゲストは、奈良県立医科大学病院の「笠原 敬」先生です!
テーマは 第4回「もともと医療や医学は個別性がとても高いものなので、SNSで議論できるようなものではありません。」をお話しいただきます。
目次
- プロフィール
- 2020年には新型コロナウイルスが出てきましたが、現場での決断や方針を示していくのは大変なことだったと思います。当時を振り返っていかがでしょうか。
- 難しいところですね。
- ドキュメンタリー番組の中でも、現場スタッフが不安で働く中で、しっかりと説明しておられる姿が見られましたが、スタッフへのマネジメントの面などで大変なことはありましたか。
- 当時、先生のモチベーションになっていたことなどはありますか。
- 奈良県立医科大学で感染症内科講座を開設されていますが、若手医師や学生に教えていくにあたり、気になることはありますか。
- 感染症の面白さを教えてください。
- 逆に感染症の難しさはどのようなところにありますか。
プロフィール

| 名 前 | 笠原(かさはら) 敬(けい) |
|---|---|
| 病院名 | 奈良県立医科大学病院 |
| 所 属 | 感染症内科 |
| 資 格 |
|
| 経 歴 |
|
|---|
ー2020年には新型コロナウイルスが出てきましたが、現場での決断や方針を示していくのは大変なことだったと思います。当時を振り返っていかがでしょうか。
新型コロナウイルスを語るのは言葉では難しいところがあります。尾身茂先生など、メディアに出ていたり、政府でやり取りをされている先生方は何人もいらっしゃいましたが、その中の多くの方々が公衆衛生の専門家であり、感染症専門医をお持ちの方は少なかったです。
やはり内閣や厚生労働省として何かをしていくというときに、例えばWHOや厚生労働省で働いていた方やそこで感染症対策をしていた方のように、政治の力学や厚生労働省の事情を分かっていないと、うまくやり取りができないと考えたうえでの人選だったのでしょうね。専門家の委員会や会議でも、公衆衛生という観点から決断や判断をする際に信頼できる人という理由が大きかったのだと思います。
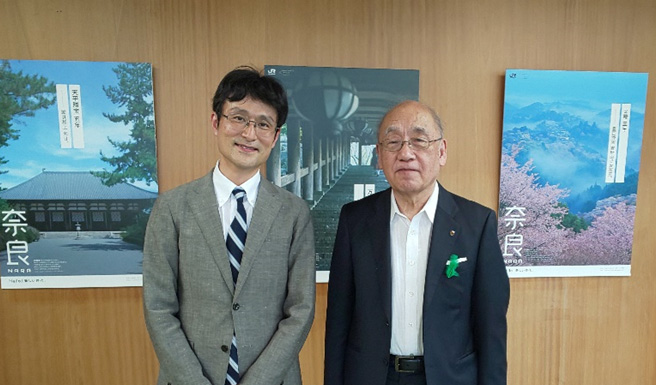
ー難しいところですね。
これをうまく言うこともなかなか難しいのですが、特に病院や患者さんにより近い現場で、色々な人に納得して行動してもらうにはなぜそう思うのか、なぜそうするのかという説明と理由がとても大事です。それにはやはり感染症という学問としての医学や医療をきちんと理解していないと説得力のある説明ができません。しかも新型コロナウイルスに関しては武漢株、アルファ株、オミクロン株と、次々に株が変わっていったり、途中からワクチンを打てるようになったり、新しい治療薬も続々と出てきたりなど、「先月はこうだったけど、今月はこうなんです」という違う決断や判断をしないといけない場面も多くありました。国からすれば2、3年ずっと同じことを言い続けたみたいな感じでしょうが、実際の現場ではそういうわけにはいきません。
「前はこんな患者さんが多かったけど、今はこんな患者さんが多い」「救急体制はどのぐらい逼迫している」「先月はこんな患者さんの救急搬送が多かった」「がんの治療や外科手術が止まっている」など、説明する根拠となるデータが実際の現場にあり、それがとても大事なんですね。医療に近いところにいて、なおかつ感染症というものがどういうものかを理解している人でないと、患者さんに現場で納得してもらうことはなかなか難しかったのではないかと思います。
行政や保健所で働きたい人、厚生労働省でそういう仕事をしたい人もいるでしょうし、感染症専門医でなおかつそういう仕事をする人もいます。感染症専門医にも色々な人がいますが、安易に専門家という言葉でくくられるのは非常に迷惑だし、止めてほしいと思っています。
ードキュメンタリー番組の中でも、現場スタッフが不安で働く中で、しっかりと説明しておられる姿が見られましたが、スタッフへのマネジメントの面などで大変なことはありましたか。
感染症という学問や医療における専門性を理解することと、マネジメントやコミュニケーションは別なのですが、基本的には患者さんへの診療ととても似ています。
PDCAサイクルのように、患者さんがどういうことをおっしゃっている、どういう状態であることから問題点を挙げて、その問題点を整理して鑑別診断を挙げ、治療してみて、その反応を見てから軌道修正していくなどのことは組織のマネジメントや行政との色々な行動に似ていますね。私は患者さんをきちんと診られる人であれば、そのスキルを応用することで、ある程度のコミュニケーションはできるのではないかと思っています。

ー当時、先生のモチベーションになっていたことなどはありますか。
どんな職業でも、その専門性において人に頼ってもらえることは最大の幸福であるという考え方に賛同します。それが人の役に立つのであれば有り難いことですし、これ以上の幸せはありませんよね。
私は感染症専門領域の人たちを代表する立場にあるので、自分の評判が悪くなると周りの人にも影響が及びますから、使命感のような気持ちももちろんありました。
ー奈良県立医科大学で感染症内科講座を開設されていますが、若手医師や学生に教えていくにあたり、気になることはありますか。
診療においては患者さんの訴えを聞いたり、あるいはほかの診療をしている方々の診療資料を収集したり、患者さんのご家族と話したり、看護師さんの看護記録を見たりなど、情報収集がまず大事です。
そして集めた情報を整理し、整理した情報からどんな診断が考えられるかという、一般的に臨床推論やクリニカルリーズニングと呼ばれるものを行います。これはモノや家電を買うときと同じです。検査をするにしても、何の検査をするのか、身体診察をどのようにするのか、カルテ記載をどうするのかなど、これらがあまりにもできていません。奈良医大だけというより、大学病院全体に言えるのかもしれませんが、これは教える側の問題が大きいですね。大学としてはそういうことを系統的に教えておらず、たまたま実習で回った先の指導医がそういうことを大事にする人だったので勉強になったというケースが多いんです。
それから、表面的なことかもしれませんが、メモを取っていない人が多いのも気になっています。人の話を聞くときにはメモを取るといった基本的なことができていません。100人いたら98人ぐらいがメモを取らないのですが、そういう人にあとから聞いたら「覚えていないです」と言うんです。この人たちは優秀だからメモを取らないのかなと思っていたのですが、実際に覚えていないんです。医学部に入っているわけですし、一般的には優秀なのでしょうが、情報が目の前を流れていくことに不安を覚えていなさそうです。メモを取ることもそうですが、情報を逃さないようにしてほしいですね。今は音声入力やChatGPTなどの生成AIもありますので、新しい技術を積極的に取り入れてやってくれたらいいのになと思っています。

ー感染症の面白さを教えてください。
感染症にはやはり微生物が存在することが学問的な意味でのほかの領域との大きな違いでしょう。がんや心血管疾患、糖尿病などはもちろん塩分、カロリー、運動など、人体の関係になりますが、感染症には第三者となる微生物が必ず存在します。そのため、微生物への介入、人体への介入、免疫力を上げる、消毒する、抗生物質を使うなどを行います。
それから微生物そのものを見つけるということもあります。どういうものが原因になっているのかなど、悪さをする微生物に対して検査を行い、それに興味を持ったり、それを正確に見つけることができるのが感染症の面白いところです。
ー逆に感染症の難しさはどのようなところにありますか。
新型コロナウイルスとも関係しますが、感染症の難しいところはやはり人に感染することです。今回のコロナ禍でも私はなるべく元気な人たちや健康な人たちのところに行き、コロナに対して、どういうふうに考えるべきかなどの話もよくしていました。「コロナには絶対にかかりたくない」「感染症怖い」という人もいれば、「コロナなんて風邪みたいなもんやろ」という人もいて、人によって意見が様々でしたが、そのような「自分だけの問題では済まない」ことに対して、専門家としてどういうふうに色々な人に寄り添うべきかというのはあまり答えのないところだと思います。
そういうとき、感染症全般という意味で、ざっくりした話をするのではなく、例えば新型コロナだったら、結核だったら、ノロウイルスだったらという話をしたり、5年前のコロナと今のコロナではどう違うのかという話をしたりします。性感染症もそうですよね。感染症の一番大きな特性は誰かから誰かに感染するといった社会学的な部分であり、個人的にはとても興味を持っています。ただ一般的な議論の根底には感染症学的な専門性が欠落していて、そのために人と人が争っているのを見ると、そこは感染症学を知っている身として、何か研究も含めて貢献できたらなとも考えています。
人類学者の話でも、前提としての感染症学の根本的な部分が若干間違っていたりすると、もしそれを知っていれば議論の方向性も違うのではないかと思うことはあります。コロナに関してはそこにワクチンが絡むので、問題が余計にややこしくなりますね。もともと医療や医学は個別性がとても高いものなので、SNSで議論できるようなものではありません。リスクコミュニケーションをどうするべきかという議論もありますが、SNSでそういう議論ができるルートを持っていること自体が間違っている可能性があります。
政府は「正しい情報を」としきりに言いますが、そもそも正しい情報とは何なのか、正しい情報を流せば問題が解決するのかという根本的な問題もあります。それに対しては時間をかけて、しっかりと議論できていないですし、「感染症専門医がいてくれて助かるね」というところになかなか繋がっていかないことに歯がゆさを覚えます。


