話題沸騰!数々の人気番組に出演している医師たちが語る
「キャリア」「信念」「未来」そのすべてに迫るインタビュー!
どのようにしてスキルを高め、逆境を乗り越えてきたのか?
日常の葛藤、医師としての信条、そして描く未来のビジョンとは――。

【出演番組一部抜粋】
命を救う!スゴ腕ドクター・Nスタ・プロフェッショナル仕事の流儀・世界一受けたい授業
今回は【東京女子医科大学病院 乳腺外科教授】明石定子先生のインタビューです!
女性医師の外科医の苦労とは。どのようにして大学教授になったのか。
乳腺外科の今後についてなど語っていただきました― ―。
第3回「子どもの頃から魚を食べるのがすごく上手かったということなんですよ」をお話しいただきます。
目次
- 1. プロフィール
- 2. 2011年に国立がん研究センター中央病院から昭和大学(現 昭和医科大学)に移られたのですね。
- 3. がんセンターと大学ではお仕事の内容は変わりましたか。
- 4. 乳がん手術はその頃に大きく変わりましたね。
- 5. 温存手術が始まってからの変化が大きかったのですか。
- 6. 中村先生はセンチネルリンパ節生検の保険適用に大きく貢献されたそうですね。
- 7. 化学療法も変わりましたか。
- 8. 先生の全摘手術のあとは再建しやすいというお話を伺いました。
- 9. 筋膜を残すこともポイントなのですか。
- 10. 手術では左手の使い方が大切だと伺いました。
- 11. 魚の食べ方が綺麗だったのですか。
- 12. やはり手先が器用でいらっしゃるんですね。
- 13. ほかにも手先が器用でいらしたエピソードはありますか。
- 14. 手先の器用さはやはり外科医として必要な要素ですか。
- 15. そして2019年に昭和大学の教授になられたのですね。
プロフィール
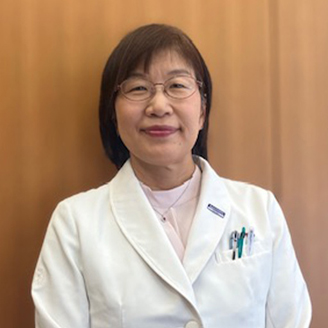
| 名 前 | 明石(あかし)定子(さだこ) |
|---|---|
| 病院名 | 東京女子医科大学病院 |
| 所 属 | 乳腺外科 |
| 資 格 |
|
| 経 歴 |
|
|---|---|
| 学 位 |
|
| 受賞歴 |
|
| 論 文 |
|
| 主な役職・活動歴 |
|
|---|
東京女子医科大学乳腺外科 明石定子教授 インタビュー
ー2011年に国立がん研究センター中央病院から昭和大学(現 昭和医科大学)に移られたのですね。
がんセンターのすぐ近くにあった聖路加国際病院の乳腺外科にいらした中村清吾先生とは色々な研究会などでご一緒する機会が多くありました。中村先生は聖路加国際病院の初代ブレストセンター長でいらっしゃいましたが、2010年に昭和大学乳腺外科の教授に就任されたんですね。そうしたご縁があり、私も昭和大学に行くことになりました。
ーがんセンターと大学ではお仕事の内容は変わりましたか。
当初は変わるのかなと思っていたのですが、案外あまり変わりませんでした(笑)。准教授でしたので、学生教育の負担がそこまで大きくなくて、どちらかと言うと診療や研究、医局員の指導といった仕事が中心でした。がんセンター時代も、自分がかつて同じ立場だったレジデントの指導をしていましたので、そこはあまり変わりなく、診療も変わりがなかったですね。大学ならではの仕事としては学生への講義が若干あったほかは実習で回ってくる学生さんに「じゃあ、これやってみる?」といった指導をする機会があるぐらいで、それまでと大幅に仕事が変わったかと言うと、それほどではありませんでした。
ー乳がん手術はその頃に大きく変わりましたね。
手術自体は時代の流れとともに変わっていきました。私がレジデントになった頃、乳房温存手術は日本における黎明期でした。同じ温存手術でもがんセンターでのやり方と中村先生のやり方には若干の違いがあったので、それぞれのいいところを取り入れつつ、工夫していきました。綺麗に温存できれば、患者さんの気持ちも明るくなりますし、外科医も満足です。手術後に出産して、母乳で子育てされた患者さんもいらっしゃいます。乳房全摘後は当然、片胸になりますし、乳房温存療法後でも放射線照射などにより授乳できなくなりますが、片方の乳房からの授乳でも立派に赤ちゃんを育てる姿を何人も拝見しました。
ー温存手術が始まってからの変化が大きかったのですか。
2000年代の初めは無理してでも乳房温存術をするような感じで、温存率が高い病院がいい病院だという風潮がありましたが、変形をめだたなくしようと努力して温存術を行っても大きく変形してしまうような症例もありましたし、何でもかんでも温存手術がいいわけではないんだという反省が出ました。そして、2013年から乳がんで乳房全摘術を行った患者さんに対する人工物による乳房再建(乳房インプラント)の保険適用が始まりました。
もう一つ大きな手術の変化はセンチネルリンパ節生検の出現ですね。これは2000年代からありましたが、2010年に保険適用になり、非常に増えました。
ー中村先生はセンチネルリンパ節生検の保険適用に大きく貢献されたそうですね。
そうですね。どのようにしたら保険適用にできるのかといった采配の仕方などが非常に素晴らしいなと思いましたし、私も勉強させていただきました。
ー化学療法も変わりましたか。
私ががんセンターのレジデントだった90年代はリンパ節転移がなければ抗がん剤はしないという時代だったのですが、アメリカではリンパ節転移陰性でも異型度が高い症例に対しては抗がん剤をしているというので、当時、腫瘍内科にいらした渡辺亨先生が大きな研究費を取って、N・SAS-BC試験を始められました。1998年から99年ぐらいのときでしたが、そのあたりで随分と変わってきて、面白い時代でしたね。もちろん今も面白い時代なのですが、大きく変わっていくなということを実感できていた時代でした。
ー先生の全摘手術のあとは再建しやすいというお話を伺いました。
それは形成外科の先生方からの評価なのですが、私としては「そうかな。そんなに違わないんじゃないのかな。皆、同じじゃないのかな」と思っています。乳がんに関しては日本乳癌学会のガイドラインに従って手術をしていますし、私だけができる手術というものもありません。でも、そんなふうに評価していただけているのは嬉しいですね。
ー筋膜を残すこともポイントなのですか。
確かに形成外科の先生方からは「筋膜が綺麗に残っているので、再建しやすい」と言っていただけますね。筋膜を残すのは患者さんの痛みが少ないというだけでなく、再発率にも差がないというデータが出たからでもあります。元々は筋膜を残したほうがドレーンを速く抜去できるという発表を聞いたからですが、そのメリットは残念ながら実感できていません。

ー手術では左手の使い方が大切だと伺いました。
がんセンターでは消化器外科なども回りましたし、そのあたりは鍛えられた点ですね。私は右利きですが、右手だけが頑張っても良い手術はできません。左手でいかに場を展開するかということが大切です。左手を添える位置やテンションをかける際の力加減を意識して、切開部位をピンと張ります。そうすると、右手は電気メスを当てるだけでいい状態になり、美しく切ることができますので、左手の使い方は大事ですね。最近、思い出したのは、私は子どもの頃から魚を食べるのがすごく上手だったということなんですよ(笑)。
ー魚の食べ方が綺麗だったのですか。
そうです。どの方向から食べていくと綺麗に身が外れて、身を崩さずに取れるのかということですね。
ーやはり手先が器用でいらっしゃるんですね。
手術と手先の器用さはあまり関係ないのかなと思っていたのですが、やはり関係しているのではないでしょうか。魚を食べるときに構造を何となくでも理解して、「こっちから、こうやって攻めると綺麗に取れるな」という技みたいなものを自然に習得して、とても綺麗に食べていました。私が食べたあとの魚には猫も振り向かないと言われていました(笑)。
ーほかにも手先が器用でいらしたエピソードはありますか。
小学生の頃は書道をしていたのですが、書道で県知事賞をいただいたこともあったので、器用だとは思っていました。
ー手先の器用さはやはり外科医として必要な要素ですか。
それは一つの要素でしかありません。手術中に冷静に判断できることも外科医として必要な要素ですし、器用さだけでは駄目だと思います。
ーそして2019年に昭和大学の教授になられたのですね。
そうですね。教授になってからは医局員の論文指導などにも力を入れました。


