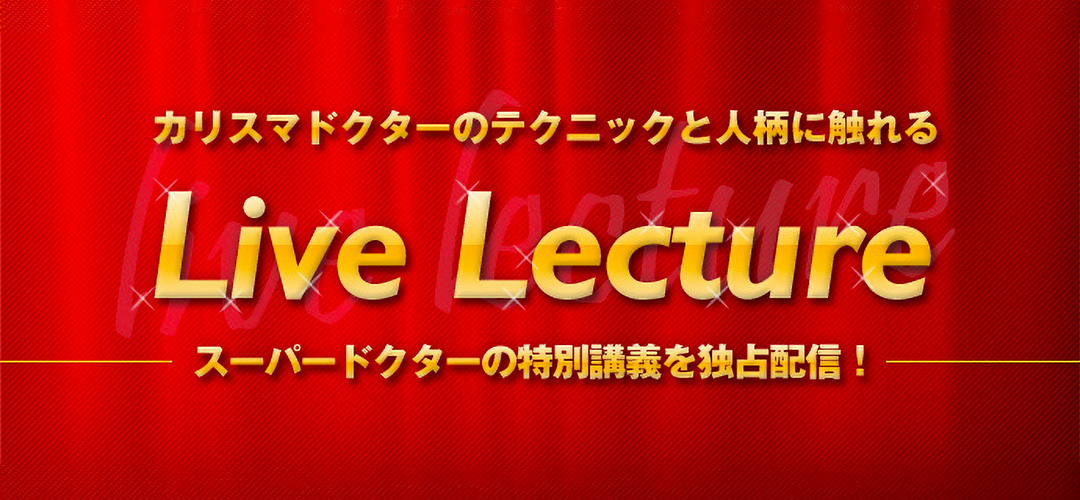
大腸外科の最先端
―― 先生は機能温存の第一人者でいらっしゃいますが、遣り甲斐はどういうところにありますか。
高橋 昔はがんの患者さんには手術でがんをたくさん取ればいい、多少障害が残っても、がんが治ればいいではないかという風潮がありました。しかし、そうではなく、機能をきちんと残しながら、良い治療を何とかうまくできないものだろうかと試行錯誤しながら開発していくのが遣り甲斐です。もう一つ、大腸がんは抗がん剤も含めて、治療をしっかりすれば再発しても病状を調整でき、治してあげられる可能性があります。再発がんに対する治療といった領域でも非常に面白い部分があるのです。以前から治療には本当に困っていたところがありましたので、そういう部分を少しずつ開発できないかと考えながら進めてきました。
―― 以前はそんなに化学療法は行われていなかったのですか。

高橋 やっていましたが、あまり効かなかった部分も多かったんです。薬が変わってから、本格的に始まりました。大腸がんの肝臓への転移はきちんと取れる状態で取れば、ある程度治せる可能性があったわけです。それに対して、治せない状態の方はどうするかということですね。通常の抗がん剤が駄目だった方に、例えば大動脈治療、肝動注化学療法というものをしてみると、思ったより効くことが分かったりなど、治療法を開発して、体系化していったのです。今は肝動注化学療法はあまり使われなくなっていますが、そういうところにもタッチしていました。私自身も勉強のために、肝臓を切る手術を執刀しました。違う領域の手術も興味深くできましたね。大腸という一つの臓器に限らず、もう少し広げた側面から治療をやっていけるところに疾患の面白さを感じました。
―― 重粒子線治療はいかがですか。
高橋 重粒子線は直腸がんの局所再発に対して、発展途上です。骨盤に再発して、その後に患者さんが亡くなられるのはミゼラブルなんです。痛みが出たり、出血したり、場合によっては神経が麻痺したりすることもあります。それを何とか救えないかと思っていたんですが、手術ではなかなか難しい場合もあります。そこで、たまたま重粒子線との出会いがあったんです。重粒子線をやると、立ちどころにがん細胞がほぼ死んでしまうんですよ。これは絶対に取れないだろうと言われていた方が重粒子線治療を行って、それからもう10年以上、再発していない人もいます。
―― 一般的な放射線治療とは全然違うのですか。

高橋 全く違います。例えば、骨盤の壁にへばりついているその外側の病気を取らないといけない状況で、骨盤を取れば、当然病気は治りますが、それでは生きていけないですよね。重粒子線では骨盤にくっついているがん細胞をピンポイントで殺すことができるんです。手術をすれば、完全に片足を引きずることになると思っていた患者さんが、重粒子線治療を受けて回復して、もう12年になります。そういう点では非常に画期的ですね。
―― どのように治療を行っているのですか。
高橋 病気の状態によっては重粒子線が適用になる方がいらっしゃいます。当院では放射線医学総合研究所と連携して、放射線医学総合研究所に患者さんを紹介することもあれば、局所再発であっても手術が可能な患者さんに関してはご紹介をいただくこともあります。今はまだそれが本当に良いのかということを研究しながら治療を行っていますが、非常に良い結果が出てきています。
―― まだ保険適用ではないですよね。

高橋 いずれは保険に通ればと思い、申請できるよう、今、色々と準備をしているところです。そう考えたら、私は大腸をやりながら化学療法もやり、放射線もある程度知っているなんて、結構な外科医ですね(笑)。
―― ガイドラインを作成なさっている先生でいらっしゃいますものね。
高橋 当院の大腸外科は森武夫先生、高橋孝先生のご功績があり、大腸がんの手術例が非常に多く、国立がん研究センター中央病院に次ぐ実績を持っています。2017年度は503例の手術を行い、そのうち456例が大腸悪性腫瘍でした。このような実績から、大腸がん治療ガイドラインの作成委員や大腸がん取扱規約の編集委員に選んでいただけたのだと思っています。大腸がん取扱規約の第7版の肝転移分類やリンパ節分類は当院の分類がもとになっていますので、そうした仕事をしてこられたことは嬉しいですね。


