
講師 石井 正
東北大学 卒後研修センター
1963年に東京都世田谷区で生まれる。
1989年に東北大学を卒業後、公立気仙沼総合病院(現 気仙沼市立病院)で研修医となる。
1992年に東北大学第二外科(現 先進外科学)に入局する。
2002年に石巻赤十字病院第一外科部長に就任する。
2007年に石巻赤十字病院医療社会事業部長を兼任し、外科勤務の一方で、災害医療に携わる。
2011年2月に宮城県から災害医療コーディネーターを委嘱される。
2011年3月に東日本大震災に遭い、宮城県災害医療コーディネーターとして、石巻医療圏の医療救護活動を統括する。
2012年10月に東北大学病院総合地域医療教育支援部教授に就任する。
現在は卒後研修センター副センター長、総合診療科科長、漢方内科科長を兼任する。
目次

総合地域医療教育支援部には家庭医を目指す先生方が集まっておられるのですか。
それはあまり偉そうなことは言えないです(笑)。総合診療科ですので、総合診療や家庭医療に携わる人を増やしましょうということで、文部科学省のコンダクター型総合診療医の養成プログラムに取り組んでいますが、東北大学はそのトップリーダーではなく、カーストでは下の方だと認識しています。その理由は東北大学が旧帝大であり、最先端医療、最先端研究に打ち込んできたゆえに、家庭医療に取り組んでこなかったことにあります。総合診療科はありますが、それは私が着任したときに格上げしたもらった診療科であり、それまでは患者さんを各科に振り分けるための総合診療外来しかありませんでした。
現在の総合診療科ではどのような患者さんを診ていらっしゃるのですか。
私どもの総合診療科の外来では色々な病院で「よく分かりませんから、宜しく」という紹介状を持ってくる患者さんを診ています。どこの病院でも分からないと言われた患者さんの「謎解き」をしますので、1日に1人か、2人で精一杯です。ときどき「本物」がいますので、手を抜けません。家庭医療が盛んな某県のある病院で診療されていた患者さんが仙台へ転居することになり「片頭痛と診断されたが、治らない」と来院されたのですが、よく調べてみますと、実は下垂体卒中だったと見破ったこともありました。
今後はどのように教育していく予定ですか。
そもそも東北大学病院は特定機能病院ですので、国の政策に則り、原則紹介状のない患者さんを診ることはなく、プライマリ・ケアの現場が救急以外は学内にありません。総合診療科では午前中に来院した紹介のない患者さんを診ているものの、救急にしても当院の救命救急センターは三次救急ですので、ウォークインの患者さんが次々に来ることもありません。したがって、家庭医療の先生方のターゲットと当院の診療対象が異なりますので、教育することが難しいんです。家庭医療は一般外来、プライマリ・ケア、在宅医療など、地域の最前線的なところですが、大学にはそのフィールドがないので、今は現場のフィールドを開拓して、そこで教育する仕組みを作ろうとしています。まずは宮城県の登米市にお願いをして、地域医療の寄付講座を作り、登米市民病院内に「総合教育センター」を設置しました。そこにできるだけ多くの学生に行ってもらうようにしています。また、宮城県内の気仙沼市立本吉病院、本吉郡南三陸町の南三陸病院にも教育する拠点を構築しようとしています。筑波大学や福島県立医科大学は以前から外の病院で教育する仕組みを作っていますが、東北大学はそれらの大学からは10年以上遅れているという認識で、一生懸命に取り組んでいます。今は総合地域医療教育支援部にて総合診療の専門医も少しずつ育ってきている状況です。

拠点ができたら、教育のあり方も変わってきますか。
病院の中で何科が診るべきか、よく分からない人を診る診療科や病院総合医は今後、とても必要になってきます。東北大学にはそうした病院総合医を目指したい人は多いかもしれませんが、家庭医療をしたい人はそれほどいません。アンケートをとると、入学時には家庭医療をしたいという学生は20%以上いるのですが、それはテレビドラマの「Dr.コトー診療所」などを見て、無医村での診療に憧れた素人だからなんじゃないかと思っています(笑)。東北大学には知的好奇心が強い学生が多く、幅広く患者さんと接して、色々な悩みを聞いたり、お世話をしたいというよりは、特定のフィールドを深掘りして勉強したい、研究したい、診療したいという人の方が多く、そのジレンマはあります。そういう大学ですから、「家庭医療万歳!」という方向にはなかなか持っていけないし、持っていくべきでもないんですよね。ただ、医学教育のガイドラインのモデルコアカリキュラムとして、総合的に診られる医師を育てなさいということになっていますし、私どもの教室を回ってきた学生に「教育する」というよりも、まずは「これからは超高齢社会になるので、専門馬鹿になっては駄目で、総合的に診る素養はいるよ」という話をしています。
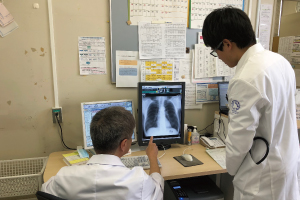
やはり病院総合医は必要なのですね。
病院総合医は今後ますます求められる存在になります。その理由は高齢化が進み、高齢者が増えるわけですが、高齢者の中に病気が1つしかないという人はほとんどいないからです。複数の疾患を抱えながら、一番のメインの疾患に対して診療されるということです。例えば、外科で言うと、食道がんの手術をする際に食道がんしかないという患者さんは少なく、高血圧や糖尿病もあったりします。そのため「糖尿病は知らないよ」ということではなく、ある程度は知識があって、ファーストタッチの診療ができる医師が必要です。病院総合医にならなくても、「俺は食道外科だから、ほかのことは一切やらない」ではなくて、「糖尿病の患者さんにはこうしましょう」というようなことを糖尿病の専門医に相談できたり、自分の専門外の分野でもある程度戦える医師が求められます。学生には「ざっくり言うと『全科当直できます』と言える医師が求められる」と教えています。ある病院でポストが一つしかない場合、「眼科医だから、全科当直はしません」という医師と「眼科医ですが、全科当直もできますよ」という医師のどちらが採用されるでしょうか。医師という職業のあり方を考えた場合はそういうプライマリ・ケアの素養は不可欠でしょう。


