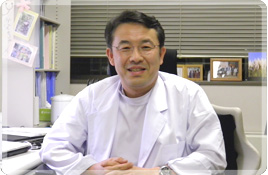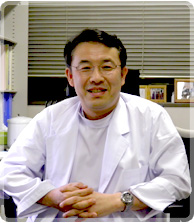
講師 岩田 広治 先生
愛知県がんセンター中央病院 副院長兼乳腺科部長
1961年に愛知県豊橋市で生まれる。
1987年に名古屋市立大学を卒業する。
名古屋市立大学医学部第2外科助手などを経て、
1998年に愛知県がんセンターに乳腺診療科医長として着任する。2003年から乳腺科部長を務め、
2012年5月に副院長を兼任する。
日本乳癌学会専門医、評議員、日本外科学会指導医、日本臨床腫瘍学会暫定指導医、日本癌治療学会、米国臨床腫瘍学会(ASCO)、日本癌学会、日本乳癌検診学会、日本臨床外科学会などに所属する。JCOG(日本臨床腫瘍研究グループ)乳がんグループ代表を務める。
Top Oncologist インタビュー
”かっこいい人”との出会いを大切にしてどこにも負けないがんセンター病院を作った”かっこいい人”

医師を目指したきっかけからお聞かせください。
高校2年生のときに「大学、どうしようかなあ」と考えていたところ、医師の息子である友人に医師の話を聞いたんです。結婚しても共働きすることもなく、奥さんを食べさせていける仕事だということにいいなと思いました(笑)。私の両親は共働きで、高度成長時代だったこともあるのかもしれませんが、母の方が父よりも高収入だった時期があり、たまに揉めていたんです。私の血縁関係には医師は一人もおらず、仕事の内容についてはよく分からないまま、医師を目指しました。
どんな学生時代を過ごされましたか。
超が付くほど不真面目な学生で、大学にはほとんど行っていませんでした。2年生から3年生への進級ができなくて、留年したぐらいです。今の医学生の皆さんにも心強く思ってもらえるはずですよ(笑)。野球部での活動、麻雀、酒で過ごした学生時代でしたね。ただ、野球はかなり頑張っていました。センターを守って、打順は1番でした。西医体で準優勝、全医体で優勝したというのが一番の自慢です(笑)。その頃の仲間とは毎年1月の終わりに、酒を飲んで1泊して、次の日にゴルフして解散という集まりを続けています。
外科医師を志したのはいつでしたか。
大学に入ってからですね。野球部の先輩で外科系に進む方が多く、第2外科の先生方が野球をされるときに審判に行っていたんです。当時の正岡昭教授がピッチャーをされていて、格好良かったですね。内科は学生時代にきちんと勉強をしていないと、仕事にならない気がしましたが、外科は「手に職」ですからヨーイドンでスタートでき、入ってからの勝負ですので、真面目に授業に出ていない私にはぴったりなのではないかと思いました(笑)。
第2外科はいかがでしたか。
当時の第2外科は「ビリから数えた方が早い人しか入ってこない」と言われていました(笑)。でも雰囲気は良かったですね。正岡教授は胸腺腫の正岡分類を発表するなど、国際的に知られた方です。コンピューターのない時代だったのに、論文の執筆も早かったですね。白髪のロマンスグレーで、靴も真っ白で素敵でしたよ。私の中で大学教授というのは正岡教授のことなんです。音楽がお好きで、「誰かピアノが弾けるやつはいるか」とおっしゃったのですが、誰もいなかったので、教授自らお弾きになったこともありました。教授退官パーティーのときは教授がピアノ、お孫さんがヴァイオリン、タカラジェンヌの方々が歌われたりして、すごかったです。野球は大の阪急ブレーブスファンで、阪急の名古屋後援会の会長をなさっていました。呼吸器外科や胸部外科のメンバーで飲みに行くと、教授ばかりがモテていましたよ(笑)。
現在の初期研修、後期研修にあたる時代に、岩田先生はどのような研修をなさっていたのですか。
卒後、大学病院1年、外の病院3年の計4年、修練を積み、5年目に大学に帰って研究を行い、学位を取得するというのが当時の第2外科の慣例でした。私は2年目は名古屋のセントラル病院、3年目は豊橋市民病院の桜ヶ岡分院に行きました。どちらの病院も既にないのですが、色々な経験をさせていただきました。セントラル病院は救急の最前線で、夜中の緊急手術も多かったですね。心筋梗塞や大動脈乖離など、内科系のことも学べました。桜ヶ岡分院は100床程度の小規模な病院で、内科、外科、小児科しかなく、膝蓋骨や大腿骨骨折の手術など、整形外科手術にも取り組みました。どちらの病院でも外科手術はすい臓や肝臓が多く、乳腺には携わっていませんでした。医師になって丸4年、乳がん手術の経験は1例もなかったのです。
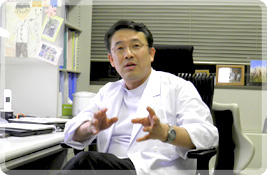
乳腺を専攻しようと思われたのはいつですか。
年目で大学に戻り、どのグループに入って、どんな研究をしようかと思っていたところ、小林俊三先生、セントラル病院でご一緒だった岩瀬弘敬先生に出会い、乳腺グループに入ることにしたのです。理不尽なことを言う先輩もいらっしゃる中で、岩瀬先生のおっしゃることはいつも理に適っていましたし、色んなことを教わりました。岩瀬先生は今は熊本大学の教授をなさっていますが、相変わらずジェントルマンですね。ですから、乳がんに興味があるというよりも、岩瀬先生のもとで働きたいというのが動機です。小林先生は第10回の日本乳癌学会の会長を務めた先生で、当時は講師でいらっしゃいましたが、乳腺グループに入るまではよく存じ上げなかったんですね。私はがんについての基礎的で、学術的な勉強に初めて取り組んだわけですが、小林先生は研究についてはあれをしろ、これをしろというタイプではなく、「何をしたいのか」と尋ねてくださる、懐の深い方でした。あるとき、新しいトピックスを小林先生に提示して、「この専門の先生が金沢にいらっしゃる」と言ったら、すぐに「うちの若いものがお話を聞きたいと言っているんですが」と電話をかけてくださったんです。そのお蔭で、金沢大学の病理学の岡田保典先生とお目にかかれ、研究データを持っては特急しらさぎで金沢まで通う日々でした。学位論文を提出するまでは臨床を行わず、研究のみで、生活費はアルバイトで賄っていましたが、楽しかったですね。

学位を取得されたあとはどちらに勤務なさったのですか。
三重県の志摩半島にあった国保前島病院が第2外科のジッツで、そこに行きました。内科、外科、整形外科のみの100床程度の病院でしたが、内科が撤退になり、外科医3人で100床を診るのは無理ということで、補充メンバーとして私が選ばれたんです。5月の連休明け、下の娘が生まれて2カ月の頃で、家族4人で英虞湾を渡る連絡船に乗って着任しました。連絡船には離島に行く雰囲気が漂い、「Dr.コトー」のような世界でしたよ(笑)。正岡教授から「岩田くんは内分泌を勉強したんだから、糖尿病や透析をやれ」と言われ、透析回路作りやシャントの手術をこなしていたほか、訪問看護ステーションの事務のスタッフが運転する車に看護師さんと乗って訪問診療に行くなど、地域医療を体験しました。海女さんが活躍する地域ですし、家の前に鮑や伊勢海老が置いてあったこともありましたね。
そして第2外科で助手になられたのですね。
前島病院には1年半ほどいましたが、研究終了後、前島病院へ赴任する前の数カ月間を大学病院で小林先生と臨床を行っていました。そのときには乳がんの専門家としてやっていこうと決めていましたね。前島病院から帰局後は第2外科で助手になり、本格的に乳腺の世界に入りました。乳がん治療に新しい風が吹き始めた頃でした。
転機となったできごとはありますか。
大学病院の患者さんがアメリカで行われていた化学療法の情報を持ってこられ、「アメリカではこれがスタンダードだ、これをやってください」と言われたのです。当時の日本ではまだエビデンスとは何ぞやという時代でしたが、できないと悔しいですし、必死に勉強しました。その頃の乳がん治療はがんのバイオロジーも明確ではなく、手術後はUFTなどの飲み薬を服用する程度でしたから、手術後に抗がん剤治療を行うこと、中でもアドリアマイシンとエンドキサンの併用を4サイクル行うという化学療法がアメリカでの標準治療だというのは衝撃的でしたね。
手術も変わってきた時代ですよね。
乳房切除から縮小の方向に向かう時代でした。京都大学の児玉宏先生が大胸筋と小胸筋は温存しつつ、リンパ節の郭清を広く行う児玉法を開発され、その術式を習いに伺ったりしたことも楽しかったです。
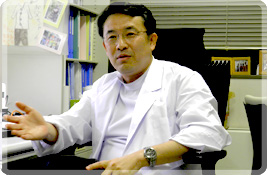
愛知県がんセンターに移られたきっかけはどういうものだったのですか。
がんセンターにいらした先生が開業され、空きができるというので、がんセンターの三浦重人先生から小林先生に名古屋市立大学から誰かをという話があったそうです。当時、私は南カリフォルニア大学に留学が決まっていました。自分でオファーを出したら、ポスドクの人が辞めたあとに来てもいいと言われ、『地球の歩き方』を買って準備していたんです(笑)。でも、小林先生から「がんセンターに行っておけ」と言われ、「分かりました」と即答しましたね。1998年、36歳のときに乳腺外科グループのナンバー4、つまり一番下のスタッフとして着任しました。
その後、42歳の若さで部長就任というのは早いですね。
がんセンター乳腺外科の先輩に岩瀬拓士先生がいらしたのですが、その当時の癌研有明病院の霞富士雄先生が「岩瀬を癌研に戻せ」とおっしゃったのです(笑)。岩瀬先生としても病理が強い癌研の方が良かったみたいで、お戻りになることになりました。愛知県がんセンターの部長職は全国公募をかけるのですが、5人の立候補者のうち、私は最年少でした。もちろん、業績なども提出しましたが、当時の院長から「岩田先生に決めた。業績は劣っていたけれど、伸びしろに賭けた」と言われ、とても励みになりました。部長になり、乳腺科と名称を改め独立しました。手術だけ、外科的なことだけではなく、薬などの内科的な治療も含めてやっていこうという気概を持っていました。
愛知県がんセンター全体で、乳がんに対して取り組んでいることをお聞かせください。
どこにも負けない、日本で一番だと言えることは治験・臨床試験の多さですね。転機は2005年に、ハーセプチンの術後治療についての論文が『The New England Journal of Medicine』に載り、その著者の一人として名前を載せていただいたことです。これが成功体験となり、その後の進むべき道が明確になりました。既存の治療のみならず、新しい治療を開発する努力を重ね、愛知県がんセンターが東海地区、ひいては日本の医療を引っ張っていく存在でありたいと思っています。
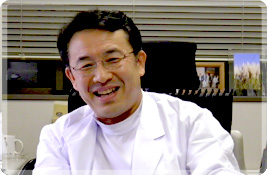
乳腺外科医としての遣り甲斐はどんなところにありますか。
私が乳腺外科を選んだのは特別な経緯があったわけではありませんが、もう一度、人生をやり直せるとしても、同じ道を進みたいですね。遣り甲斐に関しては立場によって異なります。若い頃はがんが治った患者さんから「ありがとうございました」と言われるのが遣り甲斐でしたし、部長になって以降は「愛知県がんセンターはすごいね」と言われると遣り甲斐を感じます。副院長になってからは電子カルテの導入に取り組んでいますが、新しいことにチャレンジする充実感がモチベーションに繋がるんですね。立場が変わるたびにチャレンジすべきものが待っていると思うと楽しいですし、負担ではないですね。たとえ結果が駄目だったとしても、自分の責任の範囲内でしたら何とかなるものです。
乳腺外科学の今後の展望をお聞かせください。
日本の乳がん診療でオールジャパンの仕組みづくりをしないと、欧米列国はもちろん、中国や韓国といった東アジア諸国にも負けてしまいます。狭い国土の中で仲違いをしている場合ではありません。まずは臨床試験の仕組みをオールジャパンで動かしていきたいですね。そして日本の中で目指すべきベクトルを共有しないといけません。政治と一緒で、ばらばらなところからは何も生まれてこないのです。日本の乳がん診療が良くなるための課題解決には若い医師の力が必要ですし、そのうえで全体的なボトムアップを図るための種まきを行っているところです。
医療者が心身ともに健康であるためには、どんなことが必要でしょうか。
若い研修医によく言っているのは「医師が心身ともに健康でないと、いい医療はできない」ということです。そのためには家族がごたごたしていたらいけませんので、遅くまで残らず、早く帰って家族を大切にしてほしいですね。ストレスを溜めないことも大事です。私どもの乳腺外科ではスキーツアーなどの部内の催しを活発に行っています。
研修医へのメッセージをお願いします。
人との出会いを大切にしてください。私が今あるのも、これまでの出会いが有効に働いたからなのです。医師であることを特別視せず、人として人と接するという心を忘れないでください。医療者との出会いだけではなく、患者さんとの出会いも含めて大事にしましょう。意見を言う機会があっても、組織や現状の批判しかしない人もいます。特に人の批判は止めて、建設的でクリエイティブな意見を述べてほしいと思います。そして、失敗を恐れず、チャレンジする精神を持って、頑張ってください。