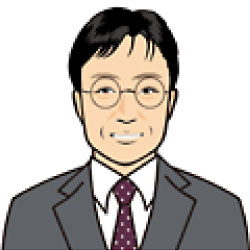
講師 千原 靖弘
内藤証券投資調査部
1971年福岡県出身。東海大学大学院で中国戦国時代の秦の法律を研究し、1997年に修士号を取得。同年に中国政府奨学金を得て、上海の復旦大学に2年間留学。帰国後はアジア情報の配信会社で、半導体産業を中心とした台湾ニュースの執筆・編集を担当。その後、広東省広州に駐在。2002年から中国株情報の配信会社で執筆・編集を担当。2004年から内藤証券株式会社の中国部に在籍し、情報配信、投資家セミナーなどを担当。十数年にわたり中国の経済、金融市場、上場企業をウォッチし、それらの詳細な情報に加え、現地事情や社会・文化にも詳しい

共産主義を標榜する中華人民共和国では、三大生産要素の筆頭格である土地が、国有あるいは集団所有となっている。個人所有の土地は存在しない。「中華人民共和国憲法」の第十条にも、“都市の土地は国家所有に属す”と明記されている。農村や都市郊外の土地は、国家所有の場所を除き、集団所有とされる。
中国で個人や法人は土地を所有できないが、土地使用権は有償で取得できる。これは定期借地権のような権利であり、最長存続期間は住宅地で70年、工業地で50年、商業地で40年。存続期間内は転売も可能だ。満期が到来すると、無償で政府に回収されることになるが、存続期間の延長を申請することも可能。土地の所有権はないが、不便もない。
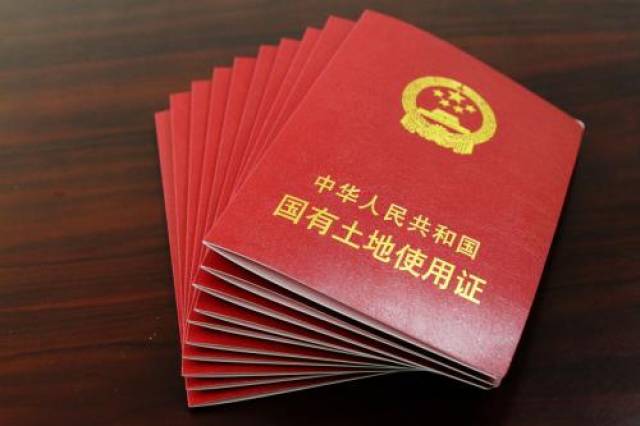
2015年に廃止され、現在は「不動産権証書」を使用
こうした制度を背景に、中国企業が保有する土地とは“期限付きの権利”であり、“無形固定資産”として貸借対照表に計上され、“減価償却が必要”。一方、日本で土地は“減価償却が不要”な“有形固定資産”。日本人にとって中国の土地制度はかなり異質と言えよう。
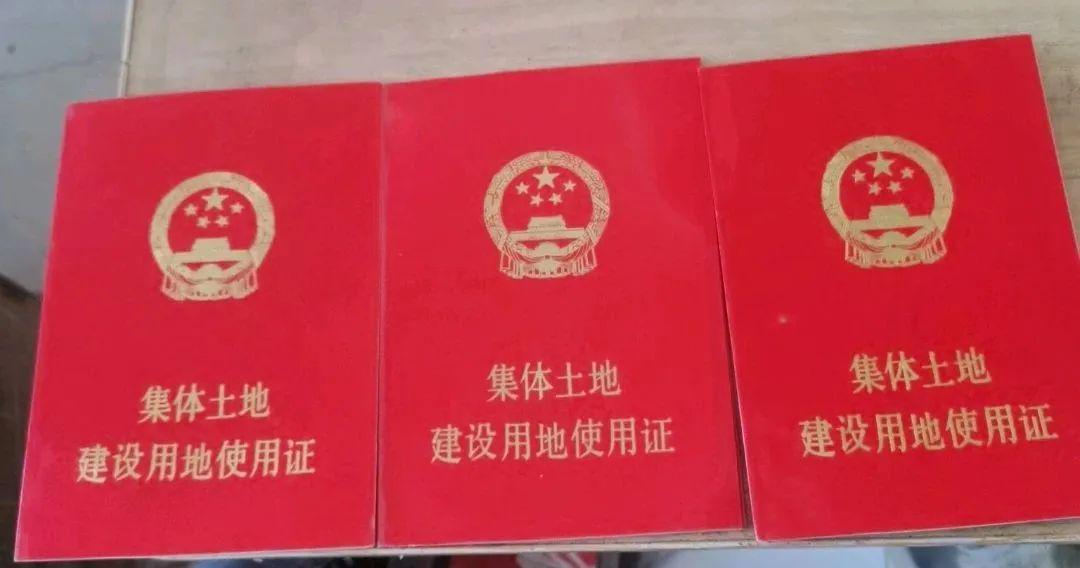
集団所有地を非農業用に使用する場合に必要
“一所懸命の土地”という言葉に表されるように、昔の日本人にとって土地とは、“先祖から継承し、子孫に伝えるべき命よりも大切な財産”だった。こうした文化的認識を背景に、中国の土地制度を恐がる日本人は多い。
しかし、世界に目を向ければ、中国の土地使用権のような制度は多い。例えば、英国の土地利用形態は、“フリー・ホールド”と“リース・ホールド”に大きく分かれる。前者は日本での土地所有とほぼ同じ。後者は中国の土地使用権に相当し、こちらの方が一般的だ。
中国の土地使用権制度は歴史が浅い。1978年12月に改革開放が始まる前、中国の土地は政府によって計画的に管理され、公有財産として無償で分配されていた。
だが、改革開放が始まると、海外企業の工場建設などに便宜を図るため、土地を賃貸することが認められた。海外企業の誘致を目指す各地の地方政府は、土地の賃貸方法を各自で研究。こうして土地使用権の原型が出来上がり、やがて国内企業にも適用された。
地方政府は一定基準を満たした企業に、所定の価格と期限で土地を賃貸していた。しかし、これでは土地の需給や適正価格が分からない。そこで、市場原理が取り入れられた。

(1987年12月1日)
深圳市の土地8588平米を525万元で落札
1987年9月に広東省深圳市の地元政府は、企業との随意契約で決まった価格で、土地使用権を譲渡。さらに同年12月には土地使用権の競売を実施し、落札価格で譲渡した。
こうした深圳市の措置は、中国で初めての試みだったが、違憲の可能性が高かった。“いかなる組織や個人も、占有、売買、その他の形式で土地を違法に譲渡してはならない”と、憲法の十条に明記されていたからだ。
そこで、1988年4月に憲法を改正し、十条に“土地使用権は法律に基づき譲渡できる”という一文を加え、現実を追認した。
地方政府による土地使用権の有償譲渡は、随意契約で売却価格を決めるのが主流だったが、それが不正の温床となったため、今日では入札や競売しか許されない。この四十年あまりで、中国は土地制度も市場化が進んだ

